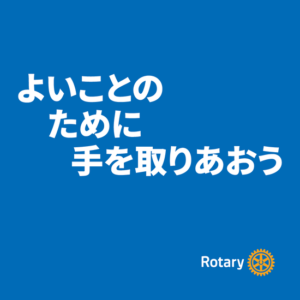2025年9月17日(水)第429回WEB例会
開会点鐘・歌の斉唱
会長挨拶

25-26年度会長
鬼頭佑介(きとうゆうすけ)
 鬼頭会長
鬼頭会長皆さん、こんにちは。第429回の例会がスタートです。
JPタワー名古屋 ホール&カンファレンスにてガバナー補佐訪問が開催されました。

皆さま、改めましてこんにちは。
愛知友愛ロータリークラブ会長の鬼頭佑介でございます。
青山 稔 ガバナー補佐、鈴木 仁志 地区副幹事、加藤 克己 分区幹事 本日は当例会にご参加頂き、誠にありがとうございます。
加えて、会場の都合により日程調整を賜りましたこと、重ねて御礼申し上げます。後ほど青山ガバナー補佐より卓話を頂戴いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
先日、春日井にて行われた第一回会長幹事会において、鈴木 康仁ガバナーはこう述べられました。
――過去13年続いたRFF(旧WFF)を終了したのは、RFFというイベントを通してポリオに貢献することも大切ですが、「各クラブがポリオに対して何ができるか」を改めて見つめ直すためである、と。
この言葉を胸に、当クラブでは9月13日に久屋大通庭園フラリエにて「ポリオ例会」を開催いたします。
名城大学ボランティア協議会の学生の皆さまをお迎えし、ポリオに関する卓話を聞いて頂き、皆さまからお寄せいただいたポリオ寄付の一部で購入した花苗を学生と共に植栽いたします。その様子は中部経済新聞にも取材いただく予定です。
さらに、当日は江南RC・岩倉RCの皆さまと合同例会を行います。
「愛知友愛ロータリークラブとしてポリオに対して何ができるのか」を改めて確認する一日にしたいと考えております。
そして本日のガバナー補佐訪問を通じ、地区の方針を学び、当クラブのさらなる発展につなげてまいります。
本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。

幹事報告

愛知友愛ロータリークラブ25-26年度幹事の小田です。
下記に幹事報告を致します。
◎ジャパンロータリーポータルサイト(ご確認ください)
マイロータリーよりも情報が見やすいです。
https://www.japanrotary.club/home
9/13(土)奉仕活動&例会
時間:9:00-12:30
会場:久屋大通庭園「フラリエ」
江南RCの皆様と合同例会となります。
当日は名城大学ボランティア協議会15名の方と岩倉RC会長の武藤様と櫻井様もいらっしゃいます。
10/9(木)ガバナー公式訪問
時間:12:30-13:30(12:00集合)
会場:ホテルルートイングランティア小牧
※江南RCさんが「ホストクラブ」です。
11/9(日)地区大会2日目
時間:13:00-17:30(12:00集合)
会場:豊川市総合体育館
※1日目(11月8日)は「会長・幹事」のみが出席です。
12/13(土) 総会&忘年会
時間:13:00-16:00(12:00集合)
会場:ラグーナベイコート蒲郡(予定)
◎当クラブの例会(メークアップが可能な例会)
上半期(7~12月)は「9月13日のみ」となります。
下半期(1~6月)は1月、3月、5月は可能です。
メークアップを希望される方は、こちらから①氏名②クラブ名➂メークアップ日をお知らせください。
8月下旬にはDCSにて提出致しました。
早急にご連絡いただき、ありがとうございました。
メークアップ&スマイル
9/3~9/16までに、29名の方にメークアップを頂きました。
佐々木康浩様、西山潤様、伊藤美樹様、稲垣孝幸様、横山要範様、小林昌弘様、豊田貴久様、尾崎秀典様、長谷川智一様、伊藤清隆様、澤田樹男様、棚橋裕様、千賀文男様、早野誠様、岡田晃一郎様、大矢伸明様、樫尾富二様、杉浦香代子様、加藤英二様、鈴木圭介様、鈴木宏政様、大岡信仁様、小笠原良様、新美俊生様、寺崎正也様、石川泰隆様、田口智様、村越和也様、柴田泰伸様
 鬼頭会長
鬼頭会長誠にありがとうございます。クラブを代表しましてお礼申し上げます。
※ご投稿頂いたあとにお支払いをされていないと証明書が発行出来ません。
メークアップをして、決済したにも関わらず「証明書が来ない」などありましたら、こちらからお知らせください。
卓話:私の旅 NO.2

卓話者:牧ケ野孝宏
2025年2月13日の卓話にて「私の旅」の話を開始しました。
前回に続き、上海勤務時代の旅を続けます。
「中国の旅シリーズ」は全部で10回あるのですが、前回は、第一回の「寧波の旅」(2009年3/28~29)をご紹介しました。
寧波が日本の歴史・文化の出発点として、古代史の中国の窓口港であったことと、日本の主食である米の最古の化石が発見された河姆渡遺跡が周辺にあることが旅の理由でした。
今回は第8回の「景徳鎮と黄山の旅」(2011年4/30~5/2)を以下にご紹介します。
景徳鎮と言えば中国の「やきもの」陶磁器そのものを思い浮かべる方が多いと思います、さて、その街はどんな所なのか?
どうして、この場所で陶磁器が作られ、世界的に有名になったのか?
今回は景徳鎮の歴史を中心に、省は跨ぎますが比較的近い世界遺産「黄山」と「安徽省の古民家一宏村」の二つを組み合わせた旅です。
上海から空路で景徳鎮空港へ約1時間で到着。飛行機が降りた滑走路を逆走して小さなターミナルビルに到着しました。
私たちを迎える看板などに陶磁器が使われていたりして「やきもの」の街にやって来た?という感じが・・・・・・。
しかしながら、この街は十九世紀後半、太平天国の乱の際に破壊され、遺跡らしいものはほとんど残っていないのです。
戦争で破壊されたのではなく、当時の景徳鎮の人々が、太平天国側に加担した為に、鎮圧した清政府が報復的に徹底的に破壊したと言われます。
街や陶磁器の工房、窯に加え、当然、職人たちも雲散霧消したことでしょうし、優秀な作品群も残ることは許されなかったと思われます。

<上海博物館にあった景徳鎮の元時代の青花陶磁器>
いまこの街の印象は、もう一度、かつての陶磁器技術を再生しようとしている学生の街のように思われました。
景徳鎮の地名は、北宋の元号に由来します。
三代皇帝「真宗」の時代(1004~8年頃)、この時期に皇帝に献納する磁器の底に「景徳年製」の四字をいれるように命じられ、その磁器が優れていた為に景徳鎮の名が残り、有名になったとのことです(第二回企画で訪問した「紹興」についても、越州と呼ばれていたのが、南宋の紹興年間に皇帝が一時滞在し「紹興」となったことと似ています)。
景徳鎮の以前の地名は「昌南(Changnan)」と言います。
中心部を流れる川が「昌江」で、その南の地方という意味のようです。
この川は揚子江に通じており、陶磁器は大運河を経由して海に運ばれ、第六回企画で訪れた「泉州」などから海外に運ばれたのです。
ラクダや馬が運んだ東西交易の主な交易品が絹で「絹の道」、陶磁器の東西交易には、大量に運ぶ為に船が使われ、海上ルートが主体で「磁器の道」、海のシルクロードの一つの重要な起点が景徳鎮です。
交易に携わる西方の人が、優秀な陶磁器を見て「どこから来たものか?」と尋ね「昌南から来たもの」と答えたことから、昌南(Channgnan)→陶磁器(China)→中国(China)となったとの話があります。
しかしながら、Chinaの語源は「秦(Qin)」の始皇帝に由来し、インドなどの周辺国でThin、Chinと発音され、英語のChinaの語源となったとする説が一般的です。
インドで起源世紀頃に中国のことを「チーナ・スターナChinaStaana」と呼んでいたと言われ、これが隋の時代に仏教がインドから伝わる際に「支那」と漢訳されたという、おもしろい現象が起きています。
中国をChinaと呼ぶのが先で、陶磁器を呼ぶ時にChinaと混在したのでしょうか?
景徳鎮が水運に恵まれた場所であると同時に、陶磁器の原料となる土に恵まれたのは当然の理由でしょう。
景徳鎮の近くの山並みが「高嶺(カオリン)」と呼ばれ(私の田舎は岐阜県飛騨の「高山」ですが、それに似た単純な山の名称ですが・・・)、これが世界に通用するKsolinという英語(高陸土・陶土・陶磁器の原料という意味)になってしまうのですから驚きです。
この山で採れる鉱石を砕いて粉にし、それを粘土上にしたもので器を整形し、乾かして薄く削り、釉薬を塗って約1300度の高温で焼いたものが磁器になります。

<有田で撮影した陶磁器>
「景徳鎮陶磁博覧区」に行くと、こうした工程が分かりやすく展示されており、また実演も行われていました。
景徳鎮の陶磁器製造の特徴は徹底された分業体制と思われます。名匠「柿右衛門」というような感じではなく、分業で出来上がったものが、最後に「景徳鎮磁器」となる感じです。

<有田の柿右衛門窯の柿木>
「白い」「薄い」「大きい」磁器が、大量に生産できることが景徳鎮の優れたところと思われます。
主に海のシルクロードを通じて西洋に伝わるのですが、これが衝撃的な影響を与え、東洋の宝物として扱われ、やがてマイセンなどの陶磁器開発に繋がってゆきます。
西洋人が驚いたのは、どうやって作るのかということではありますが、陶磁器が広く一般庶民に普及し使用されていることも驚きだったようです。
景徳鎮の栄枯盛衰を簡単に整理すると下記のようになります。
- 北宋の時代に景徳鎮の優れた白磁が認められる。当時世界一の大都市である開封の周辺にも陶磁器を作る窯が多くあり、民間に広く普及する。
- 北方の金の侵入により、北宋が滅び、杭州を都とした南宋が成立。杭州周辺の窯では優れた青磁が製造され、主流が杭州に周辺に移行。
- 元が成立。モンゴル人は「白」を尊ぶ文化を持っており、再び景徳鎮の白磁に注目。巨大な元帝国により、イラン付近で生産されるコバルトが入る。これを使って白地に絵を描いたものが青花磁器と呼ばれるもので、元の輸出振興策と呼応して世界的交易品となる。
- 元が滅び明の時代に入るとコバルトが手に入りにくくなり、代わりに色々な絵付けが主流となる。図柄のオードメイドも実施、色彩も色々と研究される。赤絵と呼ばれる技法は日本に伝わり、豊臣秀吉が朝鮮半島から連れ帰った職人らの手で確立され有田焼などになる。
- 明から清への動乱の時代に、景徳鎮産の陶磁器が輸出困難となり、オランダの東インド会社が、日本の有田焼などを代替輸入。西洋にて、積出港の「伊万里」として有名になる。
- 清の康熙~乾隆帝の全盛時に陶磁器のあらゆる記述の復興を奨励。元時代の青花などの技術を含め全盛期を迎えるが、太平天国の乱で壊滅的な打撃を受ける。
景徳鎮の今は、その歴史を誇るでもなく、山と川にたたずむ静かな街でした。
*今回の次の訪問先、世界遺産の「黄山」と「宏村」は非常に満足できる風情がありました。
「黄山」は、山頂付近での3時間半に及ぶハイキングに体力のなさを感じましたが、早朝のご来光の美しさ、刻一刻と変化する警官は全く飽きることなく、風景は異なるものの、学生時代に行ったスイス/モントルーの湖のほとりで観たアルプスと同じ感覚を約30年振りに思い起こすことができました。
次回は、第九回「開封/梁山泊/曲阜・・清明上河図と水滸伝」の旅を記載します。
以上